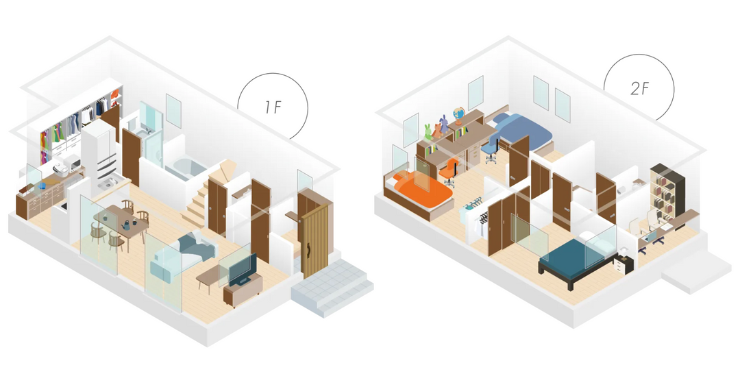固定資産税は地方税の一つであり、住宅や土地を手に入れた後に所有者に対して課税されます。
固定資産税の金額は固定資産の評価により異なるため、同じ購入価格の住宅に暮らしていても家庭によって税額が変わります。
今回の記事では、新築住宅の固定資産税と計算方法についてまとめました。
これから住宅建築を予定している方は、マイホーム取得後の税金について知っておきましょう。
固定資産税への理解を深めれば、住宅建築または購入後の資金計画が立てやすくなります。
【2025年度】新築住宅の固定資産税の軽減措置とは?
2025年度では、新築住宅の固定資産税減額措置が延長されました。
令和6年度までの措置が2年間延長され、以下のように適用されます。
- 一般の新築住宅:固定資産税が 3年間、2分の1に減額
- 3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅:固定資産税が 5年間、2分の1に減額
- 認定長期優良住宅:適用期間がそれぞれ 2年間延長(一般住宅で5年間、耐火構造住宅で7年間)
これにより、住宅購入や建築を検討している方にとっては大きなメリットとなります。
固定資産税とは

固定資産税とは、不動産などの固定資産を取得した際に支払い義務が生じる税金を指しています。
固定資産税は土地と住宅の両方に課税されるため、新築住宅を建築または購入した際には、土地の固定資産税+住宅の固定資産税を支払う必要があります。
毎年1月1日時点で土地と建物を所有している方が課税対象になり、年の途中で固定資産の所有者が変更された時には、基本的に所有期間の割合で各自の固定資産税が算出されます。
固定資産税の支払い方法には、現金の他にもクレジットカードや口座振替が選択可能な自治体が多く、毎年4〜6月頃に郵送される固定資産税の納付書を活用します。
支払いは6月・9月・12月・翌年2月の年4回に分割されており、一年分を一括支払いすることも可能です。
固定資産税の使い道とは?
私たちが、納めた固定資産税はどのように活用されているのでしょうか。
固定資産税として納税されたお金は皆さんの日々の生活を支える財源として活用されています。固定資産税は普通税(税収の使途が定められていない税)であり、徴収した市町村により、例えば皆さんが毎日使う道路や学校、友達と遊ぶ公園など、日々の生活で利用する公共施設の整備のほか、介護・福祉などの行政サービスにも使われています。(総務省HPより引用)
このように、生活をより豊かにするために活用されている大切な税金と言えます。
戸建て住宅の固定資産税の平均額
固定資産税の税額は固定資産の評価で異なるものの、一戸建てでは10〜15万円程度の税額になる場合が多いです。
ただし、税額を左右する要素はいくつも存在するため、必ずしも自宅の固定資産税が平均額の範囲に収まるとは限りません。
固定資産税は住宅建築後少しずつ減額していく
固定資産税は固定資産の評価により税額が異なります。
新築の住宅は年数が経つほど価値が下がり、同時に評価も低くなることで固定資産税の負担が減っていきます。
固定資産税の経年による減額は、「経年減価補正率」で求められ、住宅建築から20年が経過すると新築住宅の軽減措置を受けている期間と同等の固定資産税負担になる場合が多いです。
ただし、土地の評価額は経年による変更はありません。
固定資産税の計算方法と相場

固定資産税の計算方法は、以下を参考にしてください。土地と建物の両方で同じ計算式が活用されます。
購入・建築予定の土地や住宅の価格が把握できているのであれば、自分で固定資産税の目安を計算してみると良いでしょう。
土地の固定資産税の計算方法と相場
新築の固定資産税における土地の計算方法を理解するには、まず固定資産税評価額と課税標準額を算出する必要があります。
土地の評価額は、地目によって異なり、宅地は一般的に地価公示価格の約70%が基準とされます。
具体的には、宅地の評価が必要な場合、地価公示価格に70%を適用し、その後、「住宅用地特例」による減税が適用されます。
この特例は、200㎡以下の宅地の場合、課税標準額が価格の1/6に軽減され、200㎡を超える場合は、その超えた部分に対して1/3が適用されます。
新築の土地の固定資産税を具体的に計算してみます。
例えば、1,000万円の土地を購入した場合の計算は次の通りです。
まず、固定資産税評価額は次のように求めます。
固定資産税評価額 = 1,000万円 × 70% = 700万円
次に、課税標準額を求めます。200㎡以下の場合であれば、住宅用地の特例を適用します。
課税標準額 = 700万円 × 1/6 = 116万6,667円
最後に、納税額を求めるために、お住まいの地域による税率(例えば1.4%)を適用します。
納税額 = 116万6,667円 × 1.4% = 1万6,333円
実際には市町村によって地価公示価格や税率が異なるため、具体的な数値は地域の情報を基に確認する必要があります。
住宅を新築する際には、これらの計算を事前に行い、自分の納税額の目安を把握しておくと良いでしょう。
建物の固定資産税の計算方法と相場
固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」で算出されます。
ただし、一部の自治体では税率が1.5〜1.6%になる場合もあります。
評価額の目安として、建物は建設費の5〜7割、土地は時価の6〜7割が基準となります。
建物の評価額は原則として3年ごとに見直され、時間の経過とともに下がる傾向があります。
一方、土地の評価額は変更されないことが一般的です。
また、固定資産の価値が一定以下の場合(家屋が20万円以下、土地が30万円以下、償却資産が150万円以下)には課税されません。
新築の建物については、評価額は建築費の60%を基準とし、初年度の固定資産税は比較的低くなる傾向があります。
また、「新築住宅特例」により、新築戸建て住宅は3年間、マンションは5年間、課税標準額が1/2に減額されます。
例えば、建物価格2,000万円の新築住宅の場合、評価額は「2,000万円×60%×1/2=600万円」となり、税額は「600万円×1.4%=8万4,000円」となります。
ただし、特例は期間終了後に適用外となるため、その後は通常の税率で課税されます。
固定資産税の軽減措置
固定資産税にはいくつかの軽減措置があり、条件を満たせば定められた割合の減税が受けられます。
ただし、建物の軽減措置には一定の期間が設けられているため、注意してください。
軽減措置も加味した上で固定資産税の計算ができると良いでしょう。
土地に関する軽減措置
住宅用地に住宅を建築すると土地の軽減措置を受けられます。
つまり、住宅用地を空き地のままにする方が土地の固定資産税が高くなるのです。
土地の軽減措置には期間が設けられておらず、該当する土地の面積により軽減割合が異なります。
例えば200平方メートル以下の「小規模住宅用地」は、課税標準額を6分の1まで減らすことができます。
200平米を超える土地は「一般住宅用地」に該当し、固定資産税の軽減割合は3分の1に変更されます。
このような土地の軽減措置は「住宅用地の特例」と呼ばれています。
住宅に関する軽減措置
新築の住宅にも固定資産税の軽減措置が用意されています。
基本的に、新築の一戸建ては3年間、マンション購入の場合は5年間の期間、評価額の半分が軽減されるでしょう。
ただし、住宅の軽減措置には条件と期間が設定されています。
- 住宅の居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 併用住宅の場合には居住部分が半分以上を占めること
- 一戸建て以外の貸家住宅の場合には、40平行メートル以上280平方メートル以下であること
- 共同住宅は居住部分の床面積に共有部分の床面積を按分した床面積を計算すること
- 2024年3月31日までに新築された住宅であること
さらに長期優良住宅を建築した時には、軽減措置を受けられる期間が2年間延長されます。
住宅の固定資産税の軽減措置は、政府が優良な住宅の建築を促進する目的で用意しているのです。
住宅の軽減措置は毎年新しい期限が設定されていることから、最新の情報を確認しましょう。
新築住宅の評価額の決め方
新築住宅の評価額は、土地と建物のそれぞれで決まります。
土地の評価は立地や面積によって変わり、建物の評価は構造や面積が影響します。
ここでは、土地・建物の評価額や固定資産税の決定方法について解説します。
土地の評価額
土地の評価額は、固定資産税の計算において重要な要素となります。
この評価額は、主に路線価方式と倍率方式の二つの方法で決定されます。
路線価方式は、評価対象の土地が接している道路に設定された1㎡あたりの価格を基に、土地の面積をかけて計算されます。
例えば、ある地域の路線価が1万円の場合、面積が100㎡の土地の評価額は1,000万円となります。
この方式は、都市部や交通の便が良い地域に適しており、比較的正確な市場価値を反映することができます。
一方、倍率方式は、路線価が設定されていない土地に適用されます。
こちらの評価方法では、資料に基づいた倍率を用いて評価額が算出されます。
例えば、ある地域での倍率が0.5であり、評価対象の土地の基準額が2,000万円の場合、評価額は1,000万円となります。
土地の評価額は、土地の利用目的や面積、所在場所によって異なるため、具体的な計算式やデータを理解しておくことが重要です。
土地の評価は、固定資産税だけでなく、不動産の売却価値や担保評価にも影響を与えるため、定期的に見直すことが重要です。
建物の評価額
建物の評価額は、固定資産税を算出する際の重要な要素であり、具体的には固定資産評価基準に基づいて決定されます。
この評価プロセスでは、建物の構造や使用されている資材、設備の状況を考慮した家屋調査が行われます。
調査の結果、再建築費という基準が設定され、これが評価額の基本となります。
再建築費を算出するためには、再建築費評点数や経年減価補正率といった指標が用いられます。
例えば、評点数は建物の構造に応じて異なり、木造と鉄筋コンクリート造では大きな差があります。
また、設計管理費や一般管理費も評価に影響を与える要因です。
これらの要素が組み合わさることで、評価額が具体的に数値化されます。
実際の適用例として、ある木造住宅の評価額を算出する際、家屋調査によって使用している設備の質や状態が確認され、その後の評価に反映されます。
たとえば、新たに導入された省エネ設備がある場合、これがプラスの評価として考慮されることがあります。
新築住宅の固定資産税を決定する方法

新築住宅の固定資産税を決定する方法は、土地と建物それぞれに対して異なる評価基準を用いることが特徴です。
まず、住宅が所在する土地については、周辺の不動産の取引価格や地価公示価格に基づいて評価されます。
この評価は、地域ごとに異なるため、土地の特性や市場の変動が大きく影響を与えます。
次に、建物に関しては、新築された時点から1~3ヵ月後に家屋調査が実施され、評価額が算定されます。
この調査では、再建築費や建物の仕様、面積、構造などが考慮されます。
自治体の調査員が現地に訪問して詳細を確認し、適正な評価額を確定します。
所有者はこの家屋調査に立ち会うことが推奨されており、立ち会わない場合は書類に基づいた評価となります。
そのため、実際の価値よりも高くなってしまい、固定資産税が高くなる場合があります。
固定資産税を決定する家屋調査の注意点
固定資産税のもとになる固定資産評価額は、市町村の担当者が「家屋調査」を行い決定します。
「家屋調査」は強制ではないものの、立ち会い抜きの家屋調査は評価額が高く設定される可能性が考えられるため、必ず実施するようにしましょう。
家屋調査に必要な時間は30分程度になります。
調査時には、自宅の平面図を含む情報を用意しておくことをおすすめします。
また、家屋調査後の固定資産税評価額に納得ができない時には、納税通知書を受け取ってから3ヶ月以内のタイミングに限り、自治体に再調査を依頼できます。
住宅建設中など家屋調査前におおまかな評価額を知りたい方は、工事を依頼した工務店やハウスメーカーに聞くと、住宅評価額の目安を教えてもらえるでしょう。
新築住宅の固定資産税を減税したい時の申請方法
では、実際に新築住宅の固定資産税を贅言したい時には、そのように申請すればよいのでしょうか。
ここでは申請の手順を分かりやすく説明します。
①必要書類を準備する
まず、新築住宅であることを証明する書類を用意します。
主に以下の書類が必要です。
- 建築確認済証
- 完了検査証
これらは、申請時に地方自治体の指定窓口で求められるため、事前に揃えておきましょう。
②自治体の窓口を確認する
固定資産税軽減措置の申請は、多くの場合、市区町村の税務課または固定資産税課で受け付けています。
事前に窓口の場所や受付時間を調べておくとスムーズです。
③住宅の床面積を確認する
軽減措置を受けるには、新築住宅の床面積が一定の基準を満たす必要があります。
具体的には、床面積が 50㎡以上240㎡以下 であることが条件です。この情報を事前に確認しておきましょう。
④自治体窓口で申請する
準備した書類を持参し、「住宅用地等申告書」作成して自治体の窓口で申請を行います。
申請時には担当者が書類を確認し、必要に応じて追加の情報を求められることもあります。
⑤申請期限に注意する
申請は、新築住宅が完成した年度の翌年度に行うのが一般的です。
ただし、申請期限が設定されているため、自治体のルールを確認し、早めに手続きを進めましょう。
⑥軽減措置の適用内容を確認する
特例が適用されると、初年度は評価額の1/2が減額されます。
その後の年度でも軽減が続く場合があります。具体的な減額額については、自治体から通知を受けることで確認できます。
注意点
手続きを早めに行うことで、無駄な税負担を避けられるだけでなく、資金計画の見直しや生活費の調整に役立ちます。
住宅購入後は速やかに手続きを進め、必要書類の整備を徹底しましょう。
新築住宅の固定資産税の支払い方法
新築住宅を購入すると、固定資産税を支払う義務が発生します。
ただし、支払い時期や方法、期限については事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
ここでは、新築住宅の固定資産税について「いつから支払うのか」「どのように支払うのか」「支払い期限はいつまでか」を順に解説していきます。
新築住宅の固定資産税はいつから支払うか
新築住宅の固定資産税は、建物が完成した年の1月1日時点での評価額に基づいて計算され、通常、その年の4月から支払いが開始されます。
つまり、2024年に新築住宅を建てた場合、その家屋の固定資産税は2025年に初めて支払うことになります。
なお、固定資産税は毎年かかるため、支払いを忘れないようにスケジュールを立てることが重要です。
具体的には、固定資産税の決定通知書が毎年春に送付されてきますので、その内容を確認し、手続きを行う必要があります。
この通知書には、税額の明細や支払い期限が記載されています。
新築住宅の場合、初年度はしばしば軽減措置が適用されることがありますので、常に最新の情報をチェックし、不明な場合は自治体の窓口に問い合わせるのが良いでしょう。
新築住宅の固定資産税の支払い方法と期限
新築住宅の固定資産税は、地方自治体から送付される納税通知書に記載された金額を基に支払います。
支払い方法には現金納付、銀行振込、クレジットカード払い、口座引き落としがあり、現金納付は金融機関で直接支払い、銀行振込は指定口座への送金で行います。
クレジットカード払いは自治体によって利用可能で、口座引き落としは事前申し込みが必要です。
支払い期限は自治体により異なりますが、多くの場合、3月31日が一般的です。
期限を過ぎると延滞金が発生するため、スケジュール管理を忘れないようにしましょう。
また、条件によっては固定資産税の軽減措置が適用される場合があるため、事前に確認しておくことも重要です。
固定資産税の計算をシミュレーション【3,000万円の新築住宅の場合】
ここでは、固定資産税の計算方法をシミュレーションします。
3,000万円の新築住宅を購入したケースを例にしました。自分が購入・建設予定の土地や住宅に合わせて計算し直してみてください。
設定条件は以下の通りです。
- 土地の取得費:1,200万円
- 土地の固定資産税評価額:840万円
- 住宅の建築費:1,800万円
- 住宅の固定資産税評価額:1,260万円
※土地と建物の評価額は7割で計算 - 土地の固定資産税:840万円×1.4%=11.76万円
- 建物の固定資産税:1,260万円×1.4%=17.64万円
計算された土地と建物の固定資産税を合わせた額は30.38万円です。
これに固定資産税の軽減措置の計算を加えてみましょう。
- 土地の固定資産税(住宅用地の特例)11.76万円の6分の1=1.96万円
- 建物の固定資産税(新築住宅の場合)17.64万円の2分の1=8.82万円
軽減措置を計算すると、毎年の土地と住宅の固定資産税が10万円程度に収まりました。
住宅購入と同時に固定資産税の目安を知りたい方は、上記の計算方法を参考にすると良いでしょう。
建物の軽減措置が終了した後には、「住宅用地の特例」で軽減された土地の固定資産税1.96万円と、建物の固定資産税の満額である17.64万円を足した20万円程度が毎年の固定資産税になります。
ただし、多くの場合は経年による建物の評価額の減少率である経年減価補正率が適用されるため、高額ではないものの多少の減税が受けられます。
固定資産税は一戸建てとマンションで異なる
固定資産税の税額は一戸建てとマンションで大きく異なります。
なぜならマンションの土地は敷地面積をマンションの戸数で割ったものが所有区分になるため、購入価格の比率は土地より建物の方が多いのです。
また、耐用年数はマンションの方が一戸建てよりも長く設定されていることから、マンションは評価額が下がりにくいです。
それぞれの住宅の評価額により異なるものの、比較的一戸建てよりもマンションの方が固定資産税が高額であり、年数が経過しても大きく税率が下がりません。
木造の新築注文住宅はマンションより固定資産税が安い
木造の新築注文住宅とマンションでは、同じ地域内でも固定資産税に大きな違いが生じることがあります。
土地の評価額は安定していますが、建物の評価額は経年劣化により変動します。
木造住宅の耐用年数は約22年で、評価額が急速に減少するため、固定資産税も短期間で下がります。
一方、マンションの耐用年数は約47年と長く、評価額の減少は緩やかです。
その結果、初年度の固定資産税は同じ場合でも、長期的には木造住宅の税負担が軽くなる傾向があります。
また、木造住宅は建設コストがマンションより安いことが多く、初期の固定資産税も抑えられる点が特徴です。
このような理由から、固定資産税の負担を考慮する場合、木造住宅は有力な選択肢となります。
固定資産税を抑えるポイントは
固定資産税は毎年支払う税金であるため、長期的に見ると家計の大きな負担になります。
そのため、これから住宅を建築するのなら、固定資産税を抑えるポイントを知っておく必要があります。
固定資産税の軽減措置を活用しながら、税負担を少なくするためには固定資産自体を増やさないことが重要です。
例えば、実際には自分が生活スペースとして活用する予定がないガレージや物置も、屋根と3方向を囲んだ壁があると固定資産に認定される場合があります。
基礎の有無が影響を与えるルールも存在することから、住宅設備を設置または増設する際には固定資産税の対象になるかどうかを事前に確認すると良いでしょう。
さらに、固定資産税を延滞すると延滞金が請求されます。支払いの遅れに注意して無駄な出費を増やさないようにしましょう。
まとめ

固定資産税は、住宅や土地などの固定資産を入手した後に毎年必ず支払わなければいけない税金です。毎年の負担は土地と住宅の両方の固定資産税を合わせて、10〜15万円程度になる場合が多いです。
これからマイホームを建築または購入しようと考えている方は、予想される固定資産税を計算した上で資金計画を立てると良いでしょう。
また、固定資産税を抑えるためにはガレージや物置の設置が固定資産税の対象になるか確認し、必要であれば建築計画を見直しましょう。
広島・東広島・福山で理想の注文住宅を建てたいなら、広島を中心に累積1万棟を超える注文住宅を手がけてきた山根木材にご相談ください。
私たちはお客様の住まいと暮らしに寄り添うライフパートナーとして、ご家族の思いに耳を傾け、ライフステージの変化も見据えた、お客様の暮らしに寄り添ったプランをご提案します。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。